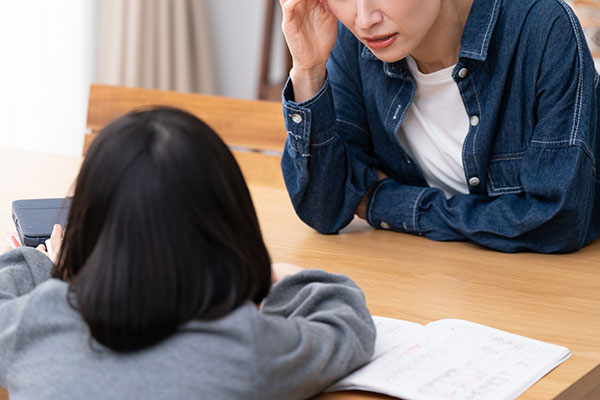発達障害とは
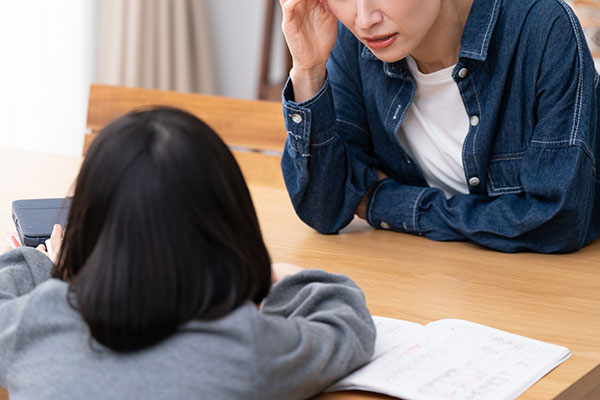
発達障害は、生まれつき脳の発達に特性があり、主にコミュニケーションや対人関係、行動のコントロールなどに困難が生じる障害の総称です。代表的なものには自閉スペクトラム症(ASD : Autism Spectrum Disorder)、注意欠如・多動症(ADHD:Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder)、限局性学習障害(SLD:Specific Learning Disorder)などがあります。
発達障害は幼少期から特徴が現れることが多いですが、大人になってから診断されることもあります。特に社会に出てから対人関係の困難や仕事のミスの多さなどが目立ち、適応の難しさを自覚するケースもあります。
近年、発達障害についての理解が進み、診断を受ける人も増えています。早期に適切なサポートを受けることで、生活のしづらさを軽減し、本人の強みを活かした社会生活を送ることが可能です。
発達障害の主な種類
発達障害にはいくつかのタイプがあり、それぞれ特徴が異なります。
1. 自閉スペクトラム症(ASD)
ASDは、対人関係やコミュニケーションの困難、強いこだわりなどが特徴です。
主な特徴
- 対人関係の困難:相手の気持ちを読み取るのが苦手、空気を読むのが難しい
- コミュニケーションの特性:言葉の裏の意味がわからない、独特な話し方をする
- 強いこだわり:同じ行動を繰り返す、予定の変更が苦手
- 感覚の過敏さ、または鈍感さ:音や光、触感などに対して強い反応をする
ASDには、知的な遅れを伴う「自閉症」や、知的な問題は認めない「アスペルガー症候群」と呼ばれていたケースも含まれます。
2. 注意欠如・多動症(ADHD)
ADHDは、不注意や多動・衝動性が特徴です。主に以下のタイプに分けられます。
- 不注意優勢型:集中力が続かない、物を忘れやすい
- 多動・衝動型:じっとしているのが苦手、思ったことをすぐに口にしてしまう
- 混合型:不注意と多動・衝動の両方の特性を持つ
主な特徴
- 忘れ物やミスが多い:仕事や学校の課題でのケアレスミスが目立つ
- 集中力が続かない:話を最後まで聞くのが難しい
- じっとしていられない:会議中や授業中に落ち着かず動いてしまう
- 衝動的な行動をする:思ったことをすぐに口に出す、順番を待てない、衝動買いが多い
ADHDは子どもの頃に目立つことが多いですが、大人になっても症状が残ることがあります。大人のADHDは「仕事が続かない」「お金の管理が苦手」などの問題として表れやすいです。
3.限局性学習症(SLD)
限局性学習症は、知的な遅れはないものの、「読む」「書く」「計算する」といった特定の学習分野に困難を抱える発達障害です。
主な特徴
- 読字障害(ディスレクシア):文字を読むのが極端に遅い、誤読が多い
- 書字障害(ディスグラフィア):文字を書くのが苦手、形が崩れる
- 算数障害(ディスカリキュリア):計算が極端に苦手、数の概念が理解しづらい
LDは知的能力とは関係なく、適切なサポートを受けることで学習の苦手さを補うことができます。
発達障害と間違えられやすい病気
他のこころの病気の症状によって、発達障害のように見えることがあります。適切な治療により症状の改善が期待できることもあるため、正しい診断を受けることが大切です。
- うつ病:頭の回転が遅くなり、忘れ物が増える
- 双極性障害:気分の波が激しく、対人関係の困難がある
- 適応障害:ストレス環境でのみ症状が出る
- 不安障害:対人関係が苦手だが、不安が原因の場合もある
- 睡眠障害:睡眠不足による集中力低下がADHDと似ることがある
上記の病気は発達障害と間違えられやすいだけでなく、発達障害と合併することもあるため、診断には専門的な知識を持った医師の診察を受けることが重要です。また、発達障害の診断には医師の評価だけでなく、幼少期のエピソードや周囲の人の評価も重要です。
発達障害の治療とサポート
発達障害は根本的に「治す」ものではありませんが、特性を理解し、適切な対策をとることで、生活のしづらさを軽減することが期待できます。
環境調整と工夫
同じ診断でも症状には個人差があるため、それぞれの特性に合った環境調整や生活上の工夫が重要になります。以下は一例です。
- ASDの場合:予定を事前に伝える、明確な指示を出す
- ADHDの場合:タスクを細かく分ける、リマインダーを活用する
- LDの場合:音声読み上げソフトや大きなマス目のノート、計算補助ツールなどを使う
また、発達障害者支援センターや就労移行支援、障害者雇用制度などの支援制度の活用も環境調整として役に立つことがあります。
薬物療法
環境調整や行動の工夫などを行っても、日常生活における支障が大きい場合には薬物療法を行う場合があります。ただし、根本的な治療ではなく、あくまで症状を和らげる目的で行われます。
発達障害による生きづらさが続くことで、「二次障害」として現れる不安や抑うつ症状などの精神症状が強い場合にも薬物療法を行うことがあります。
まとめ

発達障害は生まれつきの脳の特性によるものですが、適切な支援や環境の工夫により、得意なことを活かして社会生活を送ることが可能です。また、発達障害と似た症状を示す病気もあるため、正しい診断を受けることが大切です。
発達障害についての理解が広がることで、本人も周囲も適切に対応しやすくなります。自分や身近な人が発達障害かもしれない、と気になる場合は、医療機関や支援機関に相談することをおすすめします。